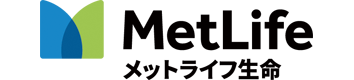掛け捨て型の死亡保険の特徴は?貯蓄型との違いや向いている方
記事公開日:2023年12月13日 / 最終更新日:2025年7月17日
死亡保険には、掛け捨て型と貯蓄型の2種類があります。それぞれ特徴が異なるため、「どちらが自分に合っているのか」知りたい方も多いのではないでしょうか。
当ページでは、掛け捨て型と貯蓄型の特徴やポイント、掛け捨て型が向いている方、必要保障額の考え方、月額保険料の目安などについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
目次
掛け捨て型の死亡保険(生命保険)の特徴とポイント
まずは、掛け捨て型の死亡保険の特徴とポイントを解説します。
特徴
掛け捨て型の死亡保険とは、保険期間が満期を迎えた際の満期保険金がなく、解約時の解約返戻金もない(あってもごくわずかである)死亡保険です。
掛け捨て型の死亡保険には代表的なものとして「定期保険」と「収入保障保険」があります。
定期保険は、保険期間内に被保険者が亡くなった場合に保険金が支払われます。
収入保障保険は、保険期間内に被保険者が亡くなった場合に、保険期間満了まで毎月一定額の死亡保険金を年金形式で受け取れる保険です。
亡くなった時点から月払給付金が支払われる仕組みのため、保険期間の経過とともに受取総額が少なくなるのが特徴です。保険会社や商品によっては、月払給付金に代えて一時金や年金として受け取れる場合もあります。
例えばメットライフ生命では、定期保険の「スーパー割引定期保険」、収入保障保険の「マイディアレスト」があります。
ポイント
掛け捨て型の死亡保険は、満期保険金や解約返戻金がない(解約返戻金の場合はあってもごくわずかである)ことで、貯蓄型に比べると保険料が割安な傾向です。保険期間が決められている分、保険料を抑えながら、必要な保障を合理的に準備できます。
定期保険のため、ライフステージに応じて保障内容の見直しがしやすいのも特徴です。ただし、一般的に年齢が上がると保険料も高くなるため、更新すると月々の保険料が上がる可能性があります。
なお、満期保険金や解約返戻金がない(解約返戻金の場合はあってもごくわずかである)こと、保険期間満了後に保障がなくなることから、「掛け捨てはもったいない」と感じる方もいるようです。
貯蓄型の死亡保険(生命保険)の特徴とポイント
次に、貯蓄型の死亡保険の特徴とポイントを解説します。
特徴
貯蓄型の死亡保険は、満期保険金や解約返戻金が設定されており、積立型保険とも呼ばれています。代表的なものに「終身保険」や「養老保険」があります。
終身保険は一生涯保障が続き、被保険者が死亡または高度障害状態になったときに保険金が支払われます。解約した場合でも、支払期間に応じた解約返戻金を受け取れるため、万一の備えと資産形成の両方が期待できます。
養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡あるいは高度障害状態になった場合は死亡・高度障害保険金、満期まで存命であれば満期保険金を受け取れる保険です。
死亡保険と生存保険(被保険者が一定期間生存していた場合に保険金が受け取れる)を組み合わせた保険を「生死混合保険」といい、養老保険はその代表的なものです。
そのほか、貯蓄型の死亡保険としては、死亡保障のある変額保険や外貨建保険、お子さまの教育資金の準備を目的とした学資保険があります。
ポイント
貯蓄型の死亡保険は支払った保険料が掛け捨てにならず、満期保険金や保障が不要になった際の解約返戻金を受け取れるのが大きな特徴です。万一の保障に加え、満期保険金や解約返戻金を活用した資産形成が期待でき、将来の備えとなります。
ただ、掛け捨て型に比べると一般的に保険料は高めです。加えて、解約返戻金は支払期間に応じて設定されるので、解約時期によってはそれまでに支払った保険料を下回る場合があります。
特に、早期の解約では支払済みの保険料を大きく下回ることもあるため、時期ごとの解約返戻金の額は事前に確認しておきましょう。
死亡保険(生命保険)の掛け捨て型と貯蓄型の違い
ここでは、掛け捨て型と貯蓄型の違いについて解説します。両者の違いは、下表のとおりです。
| ー | 掛け捨て型 | 貯蓄型 |
|---|---|---|
| 保険の種類 | 定期保険 収入保障保険など |
終身保険、養老保険、 学資保険、変額保険など |
| 保険料 | 比較的安い | 比較的高い |
| 保険期間 | 一定期間 |
一生涯あるいは一定期間 |
| 解約返戻金 | なし (あってもごくわずか) |
あり |
| 満期保険金 | なし | 満期設定のある商品はあり |
| 主な目的 | 保険料を抑えつつ、 大きな保障がほしい |
資産形成で将来に 備えつつ保障もほしい |
保険料や保険期間などがそれぞれ異なるため、目的や保障の必要性を明確にしたうえで、ご自身に合った商品を選択するとよいでしょう。
掛け捨て型の死亡保険(生命保険)が向いている方
掛け捨て型・貯蓄型それぞれの特徴を踏まえて、掛け捨て型はどのような方が向いているかを解説します。
保険料の負担を少しでも抑えたい方
掛け捨て型の死亡保険は、貯蓄型の死亡保険と比べて一般的に保険料が割安です。保険料の負担を少しでも抑えつつ、当面の保険料の負担を抑えて備えたい方は、掛け捨て型の死亡保険を検討してみましょう。
例えば、結婚や出産など、出費がかさんで保険に費用をかけられないタイミングでも、掛け捨て型の死亡保険であれば加入しやすいでしょう。
特定の期間のみ手厚い保障がほしい方
特定の期間のみ手厚い保障がほしい方は、一般的に掛け捨て型の死亡保険が向いています。
例えば、お子さまが独立するまで保障を充実させたい、定年退職までは万一のときの十分な生活資金を遺したいといった場合、貯蓄だけでは万全な備えが難しいかもしれません。掛け捨て型の死亡保険なら家計の負担を抑えつつ、万一の経済的なリスクにも備えられるでしょう。
繰り返しになりますが、掛け捨て型の死亡保険は一定の保障期間がある定期保険です。一生涯保障を受けたい方は、貯蓄型の終身保険を検討してみましょう。
ライフステージに合わせて保障を見直したい方
掛け捨て型の死亡保険は更新のタイミングで保障内容を見直すことができます。
例えば、社会人になったばかりの独身の方は扶養するご家族がいないことも多く、万一のときの生活資金を確保することが少ないでしょう。
しかし、結婚してお子さまが生まれるとご自身に何かあったときにご家族が生活できるよう、より手厚い保障内容の保険に見直そうと考える可能性もあります。さらに、お子さまが独立して夫婦2人暮らしになれば、再度必要な保障内容が変わってくるでしょう。
このように、将来のライフステージの変化に合わせて保障を検討したいなら、掛け捨て型の死亡保険を検討してみましょう。
一方の貯蓄型の終身保険は、保険料が変わらずに一生涯保障を受けられますが、掛け捨て型のようなライフステージに合わせた保障の見直しは難しい傾向にあります。必要なときに必要な保障を受けたいなら、掛け捨て型の死亡保険を検討するのも有効です。
保障と貯蓄を分けて考えたい方
あくまでも保険は万一に備える保障を重視し、貯蓄や資産形成とは分けて考えたい方も、掛け捨て型の死亡保険を検討するとよいでしょう。
先述のとおり、掛け捨て型は貯蓄型の死亡保険に比べて一般的に保険料が割安です。保険料を抑えられる分、余剰資金を預貯金やほかの資産運用に充てられます。保険は保障に特化し、資産運用は別立てで考えるという方法も取れるのです。
反対に保障と貯蓄をセットで考えたい方は、貯蓄型の死亡保険を検討するのもひとつの選択肢となるでしょう。
掛け捨て型の死亡保険(生命保険)における保険期間の仕組み
先述のとおり、掛け捨て型の死亡保険は一般的に定期保険であり、保険期間が設けられています。保険期間の設定には、被保険者の年齢で期間を設定する「歳満了」と、年数で期間を設定する「年満了」の2タイプがあります。
| 歳満了 |
|
| 年満了 |
|
長期にわたって手厚い保障を受けたいが満了まで保険料は一定がいいという方は歳満了、「お子さまが独立するまで」「住宅ローンを完済するまで」など一定期間の保障を手厚くしながら当面の保険料負担は抑えつつ、自動更新で一定の年齢まで保障を受けたい方は年満了を選択してみてはいかがでしょうか。
死亡保険金はいくら必要?
死亡保険を検討するときに、死亡保険金をいくらに設定するか悩む方もいるかもしれません。ここでは、死亡保険金の平均額や、金額を設定するときの考え方を解説します。
死亡保険金の平均額は約2,000万円
生命保険文化センターの2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、全生保(かんぽ生命を含む民間保険、簡易保険、JA、県民共済・生協等を含む)における死亡保険金の平均は1,936万円(前年2,027万円)でした。なお、民間保険のみでは1,884万円(前年1,927万円)で、いずれも年々減少傾向にあります。
必要な保障額の求め方
必要な保障額は、お子さま・配偶者の有無などの家族構成や、給付される年金、貯金額などによって異なります。次の式を参考に、万一のときの保障額の目安を把握しておきましょう。
必要な保障額=遺族が生活するうえで必要になる費用-遺族の貯金額や収入
「遺族が生活するうえで必要になる費用」には、生活費や住居費、お子さまの教育費、葬儀費用などが該当します。また、「収入」には、遺族年金などが含まれます。
必要な保障額は、遺されたご家族が生活するために足りない金額です。この不足分を死亡保険で備えるのが基本です。
ライフステージによっても必要な保障額は変わる
ライフステージによっても、必要な保障額は異なります。
例えば、独身で十分な貯蓄がある方であれば、高額な死亡保険金の必要性は低いと考えられます。自分の葬儀費用や、身辺整理にかかる費用などの最低限を準備しておくとよいでしょう。
結婚・出産によりお子さまが誕生すると、ご家族の生活費や教育費なども考慮する必要があります。また、住宅購入時は、一般的に団体信用生命保険(団信)に加入します。必要保障額に変化が生じる可能性があるため、ライフステージの変化に合わせて保障内容を見直すことが大切です。
先述の調査でも、世帯主の年齢別に死亡保険金額(全生保)の平均を見ると、お子さまの教育費などの負担が大きい30代に増加してから50代前半までが2,500万円前後となり、その後は徐々に減少しています。
死亡保険(生命保険)の月額保険料の目安
生命保険文化センターの2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、全生保における死亡保険の平均年間払込保険料は35万3,000円です。なお、民間保険のみでは35万4,000円で、いずれも月々3万円程度を支払っている計算です。
ただし、保険料は死亡保険金額や加入時の年齢、保険の商品ごとに異なります。そのため、「保険料は3万円程度になる」とは、一概にお伝えできません。
月々の保険料の目安を知りたい方はシミュレーションしてみよう
繰り返しになりますが、死亡保険の保険料は、商品の種類や加入時の年齢などにより個々に異なります。月々の保険料の目安を知りたい場合は、シミュレーションサイトを活用してみてはいかがでしょうか。
メットライフ生命の「保険料シミュレーション」では、性別・生年月日の他、希望する死亡保険金額や保険期間、健康状態に関する質問に回答するだけで簡単にシミュレーションできます。
まとめ
死亡保険は「掛け捨て型」と「貯蓄型」があり、それぞれ特徴が異なるため加入目的に応じた選択が重要です。
掛け捨て型は満期保険金や解約返戻金がない(解約返戻金の場合はあってもごくわずかである)代わりに、当面の保険料の負担を抑え、必要な保障を得られる点が魅力です。特に保険料の負担を抑えたい方や、ライフステージの変化に応じて保障を見直したい場合も掛け捨て型を検討してみてはいかがでしょうか。
メットライフ生命では、多様な保険商品を提供しており、お客さまのニーズに合わせて適切な保険を提案します。お客さまの状況に寄り添って丁寧にご案内しますので、保険の選び方がわからないという方もご安心ください。
メットライフ生命の「死亡保険(生命保険)」には、一定期間、死亡・高度障害を保障する定期保険の商品や、一生涯の死亡保障のある終身保険があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
どのような保険に加入したら良いかわからない方や、ご自身に必要な保障の選択に迷っている方などは、メットライフ生命にお気軽にご相談ください。
万が一に備えたい方向けのメットライフの商品
*1 当社所定の基準によります。
*2 当社の無配当平準定期保険の標準体保険料率(リスク細分型保険料率不適用)とリスク細分型保険料率とを比較した場合です。
保険のご相談
ぴったりな保険選びからご加入中の保険の見直し、将来の資産作りのご相談など、弊社コンサルタント社員または代理店が無料でアドバイスいたします。
電話でのご相談、お問い合わせ
専門オペレーターが、保険に関する小さな疑問にも丁寧にお応えいたします。
月~土 9:00~18:00 (年末年始および祝日を除く)