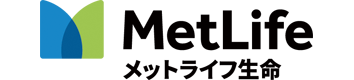未来のお金育てるガイド
未来のお金を育てるための最初のステップから、ライフステージごとに必要な考え方や解決策まで、あなたに合わせた情報をお届けするメールマガジンです。
合理的な資産形成を進めるステップとは
作成日:2023/9/14 更新日:2023/11/24
資産形成に取り組んではいるものの、なかなか思い通りに資産を増やせない方もいるかもしれません。現代はSNSや多くのメディアでお金や投資に関する情報があふれかえっていて、どの情報を信じていいか悩んでしまうこともあるでしょう。
多くの情報が飛び交う今、自分なりに情報を取捨選択し、資産形成に取り組むことが重要です。本記事では、資産形成に重要な情報を集約し、STEPごとに整理してポイントを解説していきます。
目次
将来の選択肢を広げるには
投資術の振り返り
これまで数ある投資術を学ぶだけでなく、実行して資産形成に取り組んでいるが、あまり効率良く資産が増えていない場合は、一度立ち止まってみて「この投資術で本当にいいのか」と考えてみる機会かもしれません。
特に、他人の意見に依存し過ぎたり、流行りの投資先にすぐ飛びついたりしていると、安定した資産形成が難しくなる可能性があります。
例えば、一時的に価格が上昇して話題になった金融商品に投資し、価格が急落した際に焦って売却して損をしてしまったなどはよくあることです。
もう少し合理的な投資方法を選択するために、改めてこれまで検討・実施してきた資産形成方法を振り返ってみませんか。合理的な資産形成を実現することで、今後の人生の選択肢が広がることもあるはずです。3つのステップにまとめたので、以下を確認していきましょう。
合理的な資産形成実現に向けたSTEP
STEP1 現状・将来・目標から必要なお金・期間を確かめる
資産形成を行うにあたって、自分の置かれている状況や目標金額、設定期間などを把握しておくことは目標を達成するにあたって重要な要素です。
例えば「老後のために2,000万円貯蓄したい」「マイホームを購入したい」「家族旅行に行きたい」「車を購入したい」など、資産形成の目的は人によって異なるでしょう。
現在の年齢が30歳として、目標が「老後のために2,000万円貯蓄したい」という場合は30年以上の長期計画を立てることになります。若いうちであれば、老後を迎えるまでにたっぷりと時間があり、損失が生じたとしてもリカバリーする時間があるため、ある程度リスクの高いポートフォリオを組むことができるでしょう。
一方、老後が近づくとリカバリーが難しくなるため、リスクを徐々に落としていくと安心です。そうすることで比較的安定した資産形成が期待できます。
このようにまずは現状を把握し、目標や期間を明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。これらが明確になると、そこから逆算して、目標を達成するためにどの金融商品を選択すべきかが自然と見えてくるでしょう。
STEP2 成功者に倣って投資の基本を振り返る
世の中には資産形成がうまくいき、「サイドFIREを実現した方」や「億り人」になれた方は少なからず存在します。
では、彼らは特異な投資手法を実践していたかといえば、決してそうとも言い切れません。なぜなら以下で説明する投資の基本を忠実に実践すれば、「サイドFIRE」や「億り人」のような資産形成を実現できる可能性が高まるからです。
ここでは改めて投資の基本を振り返ります。
分散投資
一つ目の投資の基本は「分散投資」です。分散投資とは、投資する資産の種類や投資のタイミング(時間)、そして地域などを複数に分散することです。これらを分散することで大きな価格変動から自身の資産を守り、価格変動リスクを軽減できます。
例えば、Aさんが100万円全てをある日本株に投資したとします。その株式が大きく下落した場合、Aさんの資産は大きく目減りします。しかし、もしAさんが100万円を日本株、外国株、債券などに分散投資していた場合、一部の株式が大きく下落しても、全体の資産価値の変動は抑えられる可能性があるのです。
分散投資は大きな損失を防ぐことが可能ですが、その反面大きく稼ぐことがむずかしくなります。したがって、高いリスクを取ってでも大きく稼ぎたい方には分散投資は向いていない投資手法といえます。
積立投資
2つ目の投資の基本は「積立投資」です。積立投資とは一定の金額で定期的(例えば毎月)に商品を買付ける手法となっています。買付け金額や商品、積立頻度などを自分で選ぶことができ、設定すれば自動で手間なく積立が可能です。
また、一定金額を定期的に買い付けることで、市場価格が高いときは少ない数の商品を、市場価格が低いときは多い数の商品を買い付けることが可能です。その結果、平均購入単価を引き下げることができます。
しかし、その一方で「価格が下がり続ける商品を選ぶと損失が拡大する」場合もあるため、きちんと理解したうえで取り組みましょう。
長期投資
3つ目の投資の基本は「長期投資」です。長期投資は、長期にわたって金融商品を保有し続けることで、複利の効果を最大限に活用できます。複利とは、投資で得た利益を当初の元本に組み入れて再投資することです。これにより、利益が利益を生み、雪だるま式に資産がふくらんでいきます。
複利は、積み立て当初は大きな力を発揮しませんが、長期で運用すればするほど大きな効果を発揮します。
一方、長期投資のデメリットはすぐに利益が発生しづらい点です。短期で売買を繰り返して利益を積み重ねたほうが短期間で大きな利益を狙えます。もし、リスクを取ってでも短期間で大きな利益を追求したい方には、長期投資は向いていないかもしれません。
STEP3 興味を持てる分野の投資方法を選択
3つ目は「興味の持てる分野の投資方法を選択する」ことです。投資の世界には数多くの金融商品が存在しています。そのなかでも興味の持てる分野の金融商品があると思います。それらを組み合わせて最適なポートフォリオを構築し、資産形成に取り組んでいくことが重要です。
以下で主な金融商品・保険商品について見ていきます。
株式投資
「株式投資」とは、株式会社に出資して利益を得る手法です。株式投資による利益とは、株価が上昇した際に得られるキャピタルゲイン(値上がり益)、企業の利益から分配される配当、そして自社の製品やサービスなどを提供する株主優待が挙げられます。
ただし、株式投資は他の金融商品に比べて価格の変動幅(ボラティリティ)が比較的大きいことや、投資している企業が倒産してしまうと価値がゼロになることもあり、比較的リスクが高い投資手法になります。
債券
「債券」は、国や地方公共団体、企業などが投資家から借り入れを行うため発行する証券です。定期的に利子が支払われ、満期になると元本が払い戻されるのが一般的です。
債券は株式や投資信託などに比べて安全性の高い投資商品といわれていますが、時価は変動するため、額面金額よりも高くなることもあれば、低くなることもあります。また、債券発行主体のデフォルト(債務不履行)リスクがあるため、元本が必ず保証されているわけではない点に注意が必要です。
投資信託
「投資信託」とは投資家から集めたお金を、投資のプロが株式や債券などに投資・運用する金融商品で、運用して得られた利益を投資家に還元する仕組みです。
投資信託は複数の異なる個別株や異なる債券などを組み合わせて、一つのセット商品として販売しているため、すでに分散投資ができている状態です。
投資信託のメリットは主に以下のとおりです。
- 100円からなど少額で始められる
- すでに分散投資がされている
このように投資信託は少額の資金で運用したい方や、リスクを分散させたい方に向いている商品です。しかし、その反面、保有を続ける限り手数料が発生する点や、売買取引に数日の期間を要する点などのデメリットも存在します。
資産形成機能のある保険
資産を増やすという目的で見過ごされることもあるのが資産形成機能のある保険商品です。この商品は上記で解説した株式などの金融商品とは異なり、万一に備えながら資産形成ができます。
代表的な商品として変額保険(有期型、終身型)があります。変額保険は、支払った保険料を保険会社が代わりに運用し、運用成果によって死亡保険金額や解約返戻金、満期保険金(有期型の場合)の額が変動する保険です。
運用成果がよければ解約返戻金や満期保険金などは増えますが、一方で成績が不調の場合には減ってしまう(死亡保険金額には最低保証あり)点や、短期間で解約すると、解約返戻金が払込保険料総額をを大幅に下回る場合もある点に注意が必要です。
また、これらの保険商品は生命保険料控除が適用されます。「生命保険料控除」は支払った保険料に応じて最大12万円(契約日が2012年1月1日以降の場合)の所得控除を活用できる制度で、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの要素から構成されています。それぞれ最大4万円ずつの所得控除が適用されます。(※1)
●本事項は税制に関する一般的な説明であり、税制は将来変更される場合がございます。(2023年11月時点)
専門家にお気軽にご相談を
保障+αの資産形成も視野に
ここまで解説してきたとおり、投資において万全な金融商品は存在しません。そのため株式投資、投資信託、債券、資産形成機能のある保険などの金融商品をバランスよく組み込み、最適なポートフォリオを構築することが重要です。
ご自身で金融商品や保険商品について学んだことだけでなく専門家に相談して、将来を踏まえた資産形成を提案してもらうことも視野にいれてみましょう。
専門家に資産形成の相談をするメリットの一つは、家計の見直しや、結婚資金の準備、住宅購入の計画、相続問題など、将来のライフプランや資金計画などについて包括的に提案してくれることです。資産形成をより合理的にすすめていけるだけでなく、幅広いお金に関する問題も解決できるようになるでしょう。この機会に一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
※本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするものであり、証券投資取引の推奨・勧誘および第三者の提供する特定商品・サービスに関して、何らかの推奨・勧誘も目的とするものではありません。
※1 出典:国税庁ホームページ「No.1140 生命保険料控除」より作成
あなたに合ったポートフォリオ構築のヒントをお金のプロがご提案します
ご負担いただく費用とリスクについて(生命保険の留意事項)
生命保険にかかる主な費用とリスクは以下のとおりです。ご負担いただく費用やその料率およびリスクの内容は、商品によって異なりますので、詳しくは各商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」などでご確認ください。
●生命保険をご契約された場合、主に次のような費用をご負担いただきます。
| 保険関係費用 |
保険契約の締結・維持に必要な費用および死亡保障などに必要な費用 |
| 運用関係費用 |
投資信託の信託報酬や信託事務の諸費用など、特別勘定の運用により発生する費用 |
| 解約控除 |
解約時や減額時などに、経過年月数に応じて積立金額などから控除する費用 |
※上記に加え、外貨建保険については、通貨交換時に為替手数料をご負担いただきます。また、外貨によりお払込みまたはお受取りいただく際は、金融機関所定の手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。
※ご負担いただく費用の合計額は、上記を足し合わせた金額となります。
●生命保険には商品の種類によって主に次のようなリスクがあります。
| 価格変動リスク |
変額保険など、国内外の株式・債券などで運用を行い、その運用実績に応じて積立金額などが増減する商品では、株価や債券価格、為替の変動などにより、積立金額や将来の年金額、解約返戻金額などが既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
| 為替リスク |
外貨建の商品では、為替レートの変動により、受取時における保険金の円換算額が、契約時における保険金の円換算額や既払込保険料の円換算額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
| 金利変動リスク |
商品によっては、運用対象となっている資産(債券など)の市場金利に応じた価値を解約返戻金に反映させるしくみになっています。そのため、解約時の市場金利の変動によっては、解約返戻金が減少し、既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
引受保険会社:メットライフ生命保険株式会社
このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などのほかの要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要などを、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
D2310-0049
お電話でのご相談
0120-026-000
月~土 9:00~18:00 (年末年始および祝日を除く)