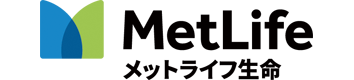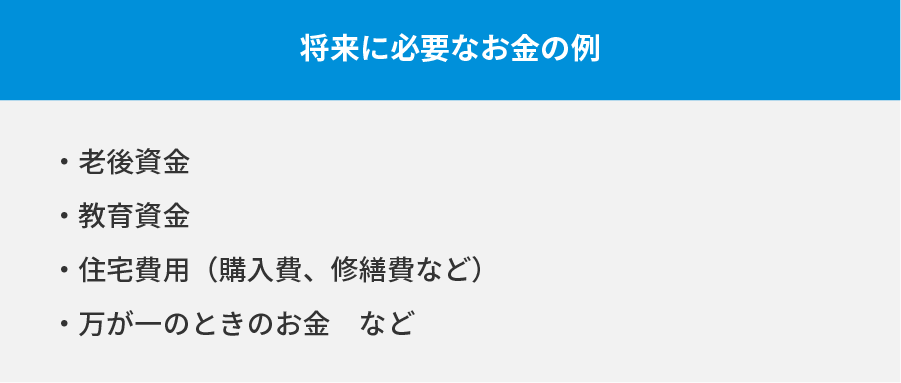未来のお金育てるガイド
未来のお金を育てるための最初のステップから、ライフステージごとに必要な考え方や解決策まで、あなたに合わせた情報をお届けするメールマガジンです。
将来に向けて必要なお金を用意するための3STEP
作成日:2023/9/14 更新日:2023/11/24
家族や自分の将来を考えるとき、貯めなければならない費用として真っ先に思いつくのは、老後の生活費や子どもの教育費などではないでしょうか。
しかし、いくら貯めればよいのか、どのような方法で貯めればよいのか、具体的な方法を一人で考えるのは、なかなか難しいものです。
お金の心配から少しでも解放されるためには、将来必要なお金について、できる限り早めに準備をスタートするのがおすすめです。
そこで本記事では総集編として、将来必要なお金を貯めるための3STEPを紹介します。
目次
将来のために必要なお金はしっかり用意しましょう
これから先、必要となるだろうお金は、世帯構成、家族の就業状況、持ち家の有無、預貯金額などにより、世帯ごとに異なります。できるだけ早く資産形成をスタートすることで、将来への準備を着実にすることができるでしょう。
お金は家族がよりよい未来を過ごすために必要なものです。もちろん、お金が全てではありませんが、いざというときにお金が足りないと、最悪の場合、家族の夢や目標を諦めざるを得ない状況に直面する可能性もあります。
将来に向けて必要なお金の準備は早めにスタートすると、その分だけ資産形成を有利に進めることができます。無理のない範囲で計画的に進めましょう。
必要なお金を用意するための3STEP
STEP 1 まずは必要なお金を可視化してみましょう
まずはそれぞれの世帯で、今後どのようなライフイベントが控えているかを把握し、それらにお金がいくらかかるのか、必要な金額を計算しておきましょう。
お金がいくら必要か試算できたら、次にお金を貯めていく手段を考えます。これから先、必要となるお金は、家計の見直しや資産運用によって貯めていくのも一つの手です。
特に家計の見直しは誰でも取り組みやすい方法です。家計簿をつけることによって収支のバランスを把握し、お金の流れに無駄がないか確認しながら節約に取り組んでみるのもよいでしょう。
STEP 2 預貯金以外の資産形成方法も検討してみましょう
お金を貯める方法として、預貯金を思いつく人も多いかもしれません。
金融広報中央委員会の調査によると、9割以上の人が預貯金を保有(※1)しており、お金を保管する場所として、とりあえずリスクの低い預貯金を選択する傾向が強いことがわかります。
ただ、現在の日本の金利では、円建(日本円)の預貯金ではお金を貯めることはできますが、お金を大きく増やすことは期待できないのが現状です。
例えば、2023年現在、定期預金の平均金利は0.02%(※2)です。100万円を預けたとしても1年後に付利される利息は、わずか159円*です。
* 利息には、一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で、利息計算時に毎回課税されています。ここでは、税率を20.3%として、簡易計算しています。
このままの金利状況が続くとは限りませんが、できれば円建の預貯金以外の方法も合わせて考えたほうが、効率的に資産形成ができる可能性が高くなります。では、具体的にどのような資産形成方法が考えられるのか、みていきましょう。
外貨預金
外貨預金は日本円を外貨に換えて預金する金融商品です。円預金と同じように、外貨普通預金や外貨定期預金などがあり、通貨によっては高い金利が適用されます。そのため、円預金より資産を増やしやすい傾向があります。
一方、外貨預金には為替リスクがあります。円と外貨を交換するときは、公示されている為替レートが適用され、円転時(外貨を円に交換すること)のレートによって為替差損や差益が発生します。
また、外貨預金は円預金とは異なり、ペイオフの対象外です。銀行が破綻した場合、預けた外貨は保護されないので注意が必要です。
投資信託
投資信託とは、投資家から集めたお金を運用の専門家が株式や債券など、さまざまな資産に分散して投資、運用する金融商品です。
個人で投資する額は少額でも、大勢の人が集まってお金を出し合うため、個人では購入できない銘柄にもファンドを通じて投資をすることが可能です。
一方、運用成果は投資先の状況や市場の動向に応じて刻々と変化するため、投資信託には元本保証がありません。元本割れした場合、損失はすべて投資家に帰属することになります。
iDeCo
iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のことで、個人が任意で加入できる年金制度です。
iDeCoを通じて、定期預金や保険商品、投資信託で運用し、原則として60歳以降に年金、一時金、年金と一時金併用方式のいずれかで受け取ることができます。
老後に必要となるお金を準備することが目的なので、さまざまな税優遇が受けられるメリットがある一方、60歳まで原則として引き出し不可というデメリットもあります。
口座管理手数料等の費用も必要になるので、加入を検討する際は確認しておきましょう。
貯蓄機能もある保険商品(資産形成型保険)
貯蓄機能もある保険商品とは、貯蓄性の高い保険商品のことです。具体的には終身保険、養老保険、個人年金保険などが挙げられます。
これらの保険は、解約時には解約返戻金、満期時に満期保険金などを受け取ることができるため、保障と貯蓄機能を兼ね備えた金融商品といえるでしょう。
一般的に、保険商品は保険証書や保険設計書などで、保険金額、解約返戻金の推移などを確認することができます。将来、受け取れる解約返戻金の目安を把握できるのは、加入者にとっても安心できるポイントです。
日々の値動きに惑わされず、着実にお金を貯めていきたい方は加入を検討してみてもよいかもしれません。
STEP3 万が一のケースも考慮しておきましょう
将来に必要となるお金は、あらかじめ想定できるものばかりではありません。突発的に起こる事態に対応するためのお金も考えておきましょう。
突然の病気や事故
思いがけない病気や予期せぬ事故は、誰しも見舞われる可能性がある事態です。病気やケガにより、手術・入院することになれば予想外の大きな出費が必要になる場合もあります。
また、入院が長引いたり、病気または事故の後遺症などで一家の大黒柱が働けない状況になったりすると、家計が一気に苦しくなることも考えられます。
日常生活のなかで起こりうる病気やケガに関しては、保険に加入することで、ある程度のリスクを回避することが可能です。
万が一の事態が起こった場合に必要な死亡保障は言うまでもなく、入院や手術、特定の治療に関して給付金や保険金が受け取れる医療保険、働けなくなったときに給付金が受け取れる就業不能保険なども検討しておきましょう。
住まいのトラブル
近年、自然災害による被害が多発しています。住んでいる地域によっては、住まいに関するリスクを優先して考えておく必要があるかもしれません。
地震や火災、水害等の被害に遭ったとき、加入している保険の適用範囲がどこまでなのかを確認しておき、不足している保障があれば追加で加入することも検討しましょう。
一人で判断するのは難しいお金のこと、まずは専門家に相談を!
将来必要となるお金は、できるだけ可視化して、何にお金が必要か、いくら必要かを確認しておきましょう。
必要なお金を貯めるためには、家計を見直すことが欠かせませんが、円建での預貯金以外の金融商品を活用することも一つの方法です。
特に貯蓄性の高い保険商品は保障を準備しながら資産形成も期待できるため、保障が必要なファミリー層にとっては活用しやすい金融商品といえるでしょう。
万が一に必要なお金も含め、自分や家族にとって将来いくら必要なのかは自分一人では判断や計算が難しい場合もあります。
お金に関する疑問やお悩みが生じたら、一人で悩まず専門家に気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
※本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするものであり、証券投資取引の推奨・勧誘および第三者の提供する特定商品・サービスに関して、何らかの推奨・勧誘も目的とするものではありません。
※1 出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和4年)」
※2 出典:日本銀行時系列統計データ検索サイトより算出(2023年11月時点)
定期預金の預入期間別平均金利
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (4) 預入金額3百万円未満
1年以上2年未満/(4)預入金額3百万円未満
年度に期種変換の上、2023年度のデータを参照
ご家族の将来のお金について、お悩みの方はお金の専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などのほかの要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要などを、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
D2310-0048
お電話でのご相談
0120-026-000
月~土 9:00~18:00 (年末年始および祝日を除く)