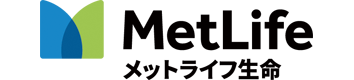未来の夢をかなえるために、資産形成の大切なSTEP~まとめ編~
作成日:2023/9/14 更新日:2025/3/21
これからの人生、家族が増えたり、新しい場所での生活や新しい仕事で成長することなど、年齢を重ねるごとにさまざまなイベントが待っているでしょう。
それらの充実したライフイベントを実現するためには、まとまった資金が必要となる場面もあります。将来に向けたお金を用意する手段の一つが資産形成です。具体的にどうすればいいのか、これまでお届けした資産形成に関するポイントを振り返りつつ、ご自身に合った資産形成の方法を見つけてみませんか。
目次
未来への備えとして、今から資産形成の準備をスタートしましょう
どのような未来を実現したいのかによって、準備が必要な金額も、そのために行う資産形成の方法も変わってくるでしょう。
なんとなく資産形成をしていては、将来のために必要なお金を用意できないかもしれません。そのため、資産形成は正しいステップを踏んで始めることが必要です。
では、将来に向けて必要なお金を用意するためにはどのようなステップで進めるべきか、振り返りながら詳しくみていきましょう。
STEP1 これから先、必要なお金をイメージしてみましょう
将来やりたいことや生活水準によって必要になる金額は異なります。マイホームが欲しい人であれば「住宅購入費」、豊かな老後を過ごしたい人であれば「老後資金」などが必要です。
まずは、ライフイベントごとにかかる主な費用を確認してみましょう。
結婚費用
一般的に挙式・披露宴・ウェディングパーティーにかかる費用は、数百万円を超えるといわれています。入籍のみ、結婚指輪や新婚旅行にお金をかけるなど、価値観で出費額は大きく変わるので、何にお金をかけるのかパートナーと相談することが大切です。
住宅資金
国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査」によると、分譲戸建て住宅の購入資金は平均4,290万円、分譲集合住宅の購入資金は平均4,716万円(※1)です。また、住宅ローンを借り入れる場合、物件の1割程度の諸費用(仲介手数料やローン手数料など)が必要になることが一般的です。
教育資金
子ども1人が幼稚園から高校卒業まで公立に通った場合にかかる教育費(学校教育および学校外活動のために支出した経費の総額)の目安は、合計で約596万円(※2)です。また、子どもが自宅から国立大学に通った場合にかかる教育費は約263万円(※3)。子どもが私立に通う場合は、さらに数百万円の費用が必要となるでしょう。
老後資金
総務省統計局が公表した家計調査報告〔家計収支編〕によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、毎月約3万7,900円のお金が不足しており、仮に老後生活が30年続くとすれば、約1,365万円もの資金が不足(※4)すると考えられるでしょう。
いずれもまとまった金額が必要となることが分かります。お金が原因で思い描いた夢や目標を諦めるのは悲しいこと。まずは、将来いくらのお金が必要となるのか具体的にシミュレーションしてみるといいでしょう。
STEP2 資産形成の基本を理解しましょう
株式などの投資商品で資産形成をおこなう場合、リスクはつきものです。運用次第では、投資に回した元本よりも資産が減ってしまうかもしれません。そのような資産形成のリスクを軽減しつつ資産を増やせる可能性を高められる3つの原則が、「積立」「分散」「長期」です。また、すでに資産形成に取り組んでいる人も、現在の投資方法がこれから紹介する3つの原則に沿っているか見直してみてもいいかもしれません。ここからは、3つの原則について、あらためて解説します。
積立投資
積立投資とは、「毎月1,000円」のように毎月一定額を継続して投資し続ける方法です。積立投資は、金融商品の価格が上昇しているときに購入口数を抑えられ、価格が下落しているときは多くの口数を購入できます。そのため、安値での買い時を逃したり高値で買いすぎたりするなどのリスクを低減できます。
分散投資
分散投資とは、さまざまな投資商品に資産を分散することでリスクを下げる投資手法です。例えば、一つの企業の株式に全資産を投資した場合、その企業の株価が下落すると資産価値が大きく減ってしまいます。一方で、10社の企業の株式を保有すれば、1社の株価が下落することによる資産価値の減少率を軽減できるでしょう。
分散投資には、異なる複数の資産を組み合わせる「資産の分散」や複数の地域や通貨を組み合わせる「地域の分散」、一度に多額の資金を投資せず時期をずらして複数回投資する「時間の分散」という考え方があります。
長期投資
長期投資とは、長期間にわたって金融商品を保有し続ける方法です。長期投資により「複利効果」を使った資産運用ができます。複利とは、運用で得た利子に対してさらに利子がつくことで雪だるま式にお金が増えていく仕組みです。
資産運用をする際には、「積立」「分散」「長期」の3つの原則を意識してみるといいでしょう。
STEP3 資産形成を始めるためには
株式や債券などに投資する場合、証券口座が必要です。証券会社や銀行などの金融機関で申込手続きをおこなって、証券口座を開設する必要があります。一般的に、ネット証券は手数料が低い傾向にあります。低コストで投資したい人や現在の資産形成を見直したい人はネット証券での口座開設を検討してみてもいいかもしれません。最近ではインターネットを通じて取引できる場合も増えているため、自分に合った環境で口座を開設しましょう。
証券口座が開設できたら投資資金を入金し、購入したい投資商品の注文をおこないます。また、保険で資産形成を始める場合は、証券口座の開設は必要ありません。保険の契約を締結すれば資産運用を始められます。
自分に合った資産形成方法を選択しよう
資産形成の方法はさまざまです。そのため、人によって適した資産形成の方法は異なります。金融商品には、元本が減らないかどうかを示す「安全性」、どのくらい収益が期待できるか「収益性」、お金を引き出しやすいかどうかを示す「流動性」という3つの基準があります。
安全性と収益性、収益性と流動性は両立が難しい関係であること、そして流動性と安全性は併存できる関係であることを覚えておきましょう。
3つの基準を兼ね備えた金融商品はありません。各商品にはそれぞれメリットやデメリットがあります。商品ごとの特徴と、自身の目的を照らし合わせることで、自分に合った資産形成方法を選びやすくなるはずです。資産形成の目的やリスク許容度に合わせて、自分に合った金融商品を選択するといいでしょう。
資産形成の成功例と失敗例
「資産形成に興味はあるけれど、失敗したらどうしよう」
「自己流で資産形成をはじめてしまったが、このままで大丈夫だろうか?」
そんな不安を抱えている方もいるでしょう。ここでは資産形成を継続していくにあたって知っておきたい、成功例と失敗例をご紹介します。
成功例:生活防衛資金を確保したうえで、長期間の積立投資をおこなっている
手元の資金を全て投資に回してしまうと、万が一の事態が起こったときに困ることがあります。そのため、投資をおこなう前に、生活防衛資金は確保しておきたいものです。
生活防衛資金とは、不測の事態に備えて確保しておくお金のことです。病気やケガで仕事がままならない場合や、自然災害に見舞われたとき、失業など、予測できないリスクに直面した際、金銭的な不安を軽減するための資金です。生活防衛資金は、一般的に生活費3~6ヵ月分程度といわれています。
また、積立投資は、積立期間が長いほどより安定した運用が可能だといわれています。さらに、長期間の運用は複利効果による資産額の増加が期待できます。
万が一に備えた「生活防衛資金を確保」しつつ、リスクを低減する効果が期待できる「長期間の積立投資」を実践することは、初心者の方でも上手に投資と付き合っていける一例といえるでしょう。
失敗例:一つの銘柄や金融商品に集中的に投資をしてしまう
自分の資産をすべて一つの企業の株式で保有している場合、保有している株式の価格が高騰すれば高い収益が期待できる一方で、株式の価格が下落すれば大きな損失を覚悟しなければならないでしょう。
リスクとリターンは表裏一体です。一つの金融商品だけに投資していると、リスクを分散することができず、損失が出た際、大切な資産を減らすことになるので注意が必要です。
また、資産運用において「安全性」を重視する人が比較的リスクの高い株式のみを保有している場合などは、自分に合った資産運用方法とはいえないでしょう。
成功例と失敗例を見比べながら、ご自身に合った資産形成方法を検討してみるのも一つの手です。
専門家に相談しながら、自分に合った資産形成を
資産形成のステップや、自分に合った資産形成方法の見つけ方をご紹介しましたが、「私にぴったりの資産形成方法って?」と悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
何にお金をかけたいのか、結婚するのか、老後はどう過ごしたいのかなど、考え方や生活によって、将来必要となるお金は異なります。資産形成方法は、人それぞれ。分からないことがあれば専門家に相談しながら、資産形成に取り組んでみてはいかがでしょうか。
※本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするものであり、証券投資取引の推奨・勧誘および第三者の提供する特定商品・サービスに関して、何らかの推奨・勧誘も目的とするものではありません。
※1 出典:国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査」より抜粋
※2 出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査-結果の概要」より算出
在学期間を幼稚園(公立)3年、小学校(公立)6年、中学校(公立)3年、高等学校(全日制・公立)3年として算出。金額は千の位を四捨五入して表記
※3 出典:独立行政法人日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査結果」より算出
1-1表 居住形態別・収入平均額及び学生生活費の内訳(大学昼間部)
区分「国立・自宅」の小計(学費)を在学期間4年として算出。金額は千の位を四捨五入して表記
※4 出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2023年(令和5年)平均結果の概要」より算出。金額は千の位を四捨五入して表記
ご自身に合った資産形成方法でお悩みの方は、お金のプロに相談してみてはいかがでしょうか?
おすすめ記事
このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などのほかの要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要などを、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
D2411-0008
お電話でのご相談
0120-026-000
月~土 9:00~18:00 (年末年始および祝日を除く)