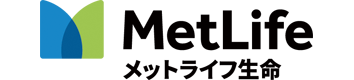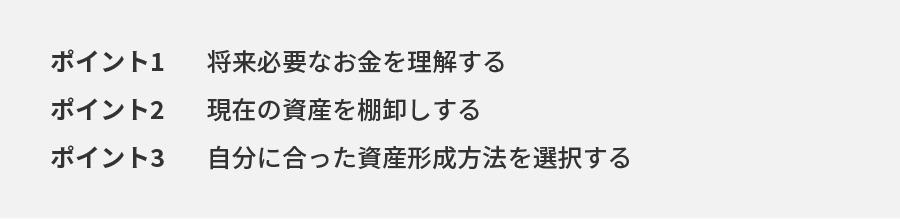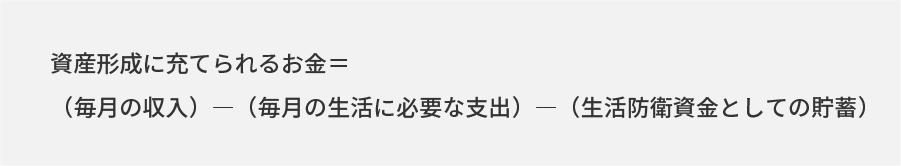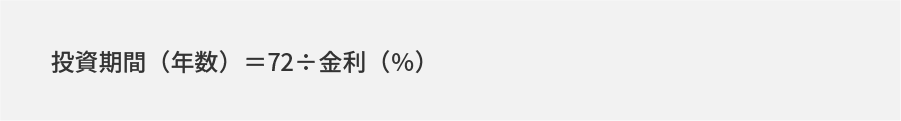自己流の資産形成で大丈夫?将来、後悔しないために押さえておきたい資産形成のポイント
作成日:2023/8/30 更新日:2025/3/21
長引く物価高による家計の負担や、少子高齢化にともなう年金の目減りの不安など、お金にまつわる不安が尽きない昨今。これまで以上に保険や投資を活用した資産形成に関心を持っている人もいるかもしれません。
自己流で資産形成をしていると、思わぬ落とし穴や損失に直面する可能性も。将来後悔しないためにも、本当に今の資産形成の方法がベストなのか、検証してみることが大切です。本記事では、後悔しない資産づくりのために押さえておきたいポイントを紹介します。
目次
なんとなく資産形成をしていませんか?自己流の資産形成にはリスクも
貯蓄や投資など自己流の方法で資産形成をしている人の中には、「資産形成について十分知っている」と思っている人もいるかもしれません。しかし、資産形成の方法は選択肢がとても多く、投資のプロも手法は人それぞれ異なります。
知識不足や曖昧な理解のままで、なんとなく資産形成方法を決めてしまってはいないでしょうか?もちろんなんとなく決めて、うまくいくこともあるでしょう。
ただし、ライフステージによって、資産形成の方法をチューニングしながら、その時々で自分や家族のライフスタイルに合った方法を選択することが必要です。その選択を間違わないためにも、最低限のルールを知っておく必要があります。
一つは「資産形成のために使える金額を正しく把握すること」です。資産形成を目的にしてしまうと、家計を無理矢理やりくりしてお金を捻出するなど、日々の生活に支障をきたしかねません。本末転倒にならないためにも、「現実的に資産形成に回せるお金」を算出することが重要です。
もう一つは「資産形成に関する知識・リスクを正しく理解すること」です。資産形成の代表的な方法は「貯金」ですが、今は低金利の時代なので、銀行にお金を預けているだけではほとんど利息がつきません。2025年1月時点の普通預金金利は年0.097%(※1)なので、100万円を預けても1年で970円の利息のみ。(税引き前)
もちろん貯金だけで将来の資産を十分確保できる人もいるでしょう。ただし、もし将来物価が上昇したら、同じ金額で買えるモノの量が減り、お金の価値が下がることになります。つまり、実質的に資産が目減りしてしまうというわけです。
そうした事態に備えて、個人年金保険や投資信託などへの資産運用で資産の増加を狙うことも一つの手です。
いずれにしても、資産運用に利用している金融商品の知識が曖昧なままでは、自分の資産の状況を理解できないはずです。そのため、損をしてしまうタイミングで保険を解約したり、投資信託を売却したりと、将来の資産形成を目指していたつもりが、裏目に出てしまいかねません。それが、自己流のリスクとも言えるでしょう。
将来の資産形成を目指すうえでは、投資のリスクを踏まえて「なぜその金融商品を購入しているのか」を自分なりに納得してから投資することが、何よりも重要です。
資産形成で押さえておきたいポイント3つ
では、将来後悔しないために押さえておきたいポイントを詳しく見ていきましょう。主に3つのポイントがあります。
<ポイント1>将来必要なお金を理解する
現在の家計や家族構成などを踏まえ、ライフステージごとに必要なお金を試算してみましょう。今後の自分の人生に必要なお金をある程度明確にすると、具体的な目標を立てやすく、資産形成の方法を具体的に考えやすくなります。必要な金額から逆算して資産形成の方法を選択することで、具体的な行動に落とし込みやすくなるはずです。
ライフステージは、大きく「単身の期間」「結婚・子育て期間」「子どもの独立後」「リタイア後(老後)」に分類できます。
生活費は、毎月発生している支出費用をもとに試算できます。主には「家賃」「食費」「光熱費」「被服費」「通信費」などです。家計簿をつけておくと、試算しやすくなるでしょう。
また、子育て家庭の場合、子どもの学費なども加味して試算しましょう。
<ポイント2>現在の資産を棚卸しする
今の資産をできるだけ正確に把握しましょう。銀行預金だけではなく、貯蓄型の生命保険や不動産、自動車など、Excelや資産管理アプリなどを活用しながらお金になりそうなものを棚卸しすることで、資産を具体的な数字で明らかにします。
棚卸しをしたうえで、資産の合計から住宅ローンなどの負債を引いた額が、現在手元にある純資産です。純資産は将来の資産形成の計画を立てるために、重要な目安になります。
純資産を把握できたら、次に将来必要なお金とのギャップを計算してみましょう。それにより、これからの収入だけでそのギャップを埋められるのか、投資などで積極的な運用にチャレンジしたほうがいいのか、考えやすくなるはずです。
<ポイント3>自分に合った資産形成方法を選択する
資産形成の計画を確実に実行していくためには、自分の収入やライフスタイルに合う方法を選択し、目標に届くまで継続することが重要だと言われています。「毎月いくらのお金を資産形成に投入できるのか」「どれくらいの期間で資産を築いていくのか」という2つの観点を踏まえて、自分に合う資産形成を検討するといいでしょう。具体的な方法は次の通りです。
(1)資産形成に充てられる資金を算出
資産形成に充てられるお金は、次の計算式で求めることができます。
毎月の生活に必要な支出は、家賃や水道光熱費などの固定費と、食費や医療費などの変動費の平均を足し合わせた金額です。生活防衛資金とは、万が一、勤め先の会社が倒産して収入が途絶えたり、ケガや病気で働けなくなったりしたときの資金のことです。
生活防衛費については、一般的に毎月の生活に必要な支出の1年分程度が目安だと言われています。毎月の支出が30万円であれば、360万円です。もし資産がマイナスになってしまうようであれば、支出を見直す、あるいは生活防衛資金を貯めてから、資産形成を考えるといいでしょう。もし「生活防衛資金は貯まっていないけど資産形成は早めにスタートしたい」という場合は、万が一に備えて収入保障保険などを検討するといいかもしれません。
(2)資産形成に充てられる期間を算出
自分にとっての資産形成の「ゴール」を決めて、そこから逆算して資産形成の方法を絞っていきましょう。例えば、仕事をリタイアし、年金受給年齢を65歳で設定すると、資産形成に必要な期間が明らかになります。その期間に応じた資産の運用を検討することができます。
もし投資で資産形成を検討している場合、「72の法則」を参考にするといいでしょう。72の法則とは、金融商品に投資する際に、金利の複利効果で元本を2倍にするために必要な期間を概算できる計算式です。
例えば、銀行の普通預金金利0.097%(※1)で元本100万円を運用した場合、2倍の200万円にするために、約742年(=72÷0.097)の投資期間を要します。一方、年利3%で運用した場合には約24年(=72÷3)で済みます。もちろん高い利回りを期待できる金融商品は、一般的に価格変動のリスクも高くなるので注意が必要です。
(3)資産形成に関するリスクやリターンに対するスタンスを考える
資産形成の方法としては、「貯金」「保険」「投資信託」「株式」などがあります。貯金についてはすでに触れたように、銀行に預けたままにしていては金利が低いため、資産を大きく増やすことは困難です。
一方で、貯蓄型や個人年金などの保険は、高度障害など万が一に備えながら、保険期間満了時に元本を超える満期保険金を受け取れるものも多いです。
NISAやiDeCoで選べる金融商品として注目されている投資信託は、一般的に保険よりもリスクが高く、株式よりもリスクが低いと言われています。ただし、経済や市場の動向によっては、元本割れの可能性もあります。
また、株式は売買の手法や企業分析など勉強することが多い反面、勉強したからといって確実に資産を増やせる約束はありません。
こうした金融商品ごとのリスクやリターンをどう捉えるかによって、選択肢は変わってきます。もし元本割れのリスクをなるべく抑えつつ、資産運用をしたい場合は、保険の活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
特に家族がいる働き世代は、万が一の保障と資産形成を両立させながら、計画を立てることが重要です。もし加入中の保険がある場合は、保険料や保障内容の見直しを図るといいかもしれません。
資産形成のポイントを意識して、今から明るい未来の構築へ
資産を増やす方法はいろいろありますが、自己流はリスクがつきものですし、後悔することもあるかもしれません。まずは、いろいろな情報に触れて、よく検証して選ぶ必要があります。
自分に合った資産形成方法を選ぶためには、毎月の資金や目標の期間を考慮することも重要です。自分がどれくらいの資金を資産形成に充てられるのかを算出し、生活の安定を保つための備えも忘れずに。
また、どれくらいの期間をかけて資産形成を進めるのかも考慮する必要があります。その上で、資産運用の方法を検討してみるといいでしょう。こうしたポイントを押さえておけば、きっと自分の目標に合った、後悔しない資産形成につながるはずです。
※1 出典:日本銀行時系列統計データ検索サイト
預金種類別店頭表示金利の平均年利率等(月次)
2025年1月のデータを参照
自分に合った資産形成で悩んだら、お金の専門家に相談してみませんか?
おすすめ記事
このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容のすべてが記載されているものではありません。また表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。保障内容などのほかの要素も考慮し、総合的にご検討ください。商品の詳細はパンフレットや契約概要などを、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。
D2501-0006
お電話でのご相談
0120-026-000
月~土 9:00~18:00 (年末年始および祝日を除く)